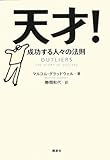最近、うちの娘から「あの人、マジ、カミだから」という言葉をよく聞きます。
「カミ=神=天才」という意味で、最近の若い人たちはよくこういう表現をします。
(こんな解説をすること自体、自分がオヤジになってきたということなのですが・・・)
このカミ、つまり天才といわれる人が生まれる法則を解き明かした本があります。
マルコム・グラッドウェルの「天才!」(勝間和代訳)です。
この本ではまず、著者のマルコムが、カナダのアイスホッケーのカミ、つまり天才と呼ばれる選手の生まれ月を調べるところから始まります。
ここで、おもしろい法則がわかるのです。
選手の誕生月は圧倒的に1,2,3月に集中しているのです。
カナダでの学年分けは、1~12月で1学年としています。
天才と呼ばれるスポーツ選手は、みんな、小学生などの早い時期からその競技始めています。
そんななか、同学年で比較すれば、早く生まれて、早く成長している体格のいい子供が、強化選手に選ばれます。
選ばれた結果、圧倒的な練習を課されることになり、同世代とますます差をつけて天才にまで達するというのです。
マルコムが言いたいことは、のちに「天才!、カミ!」と呼ばれるようになる人たちも、生来の資質というよりは、その後におかれた「環境と練習量」によるところが大きいということです。
だから人を観るときには「その人の才能や資質より、その人の置かれた環境やコミュニティを観よ」というのです。
その天才になるまでの練習量は「1万時間」であると説き、これを「1万時間の法則」と呼んでいます。
つまり、1日3時間を10年間続けるという計算になります。
例えば、モーツアルトは、6歳から作曲をはじめましたが、傑作を世に送り出すようになるまでに20年かかっています。こうなると、天才モーツアルトも、実は遅咲きだったとも言えるわけです。
ビートルズだって、ハンブルグの無名時代に、クラブで1日8時間演奏という過酷な経験があったからこそ、歴史的なバンドに成長したということになります。
これはIT業界にも言えます。
マイクロソフトのビル・ゲイツ、アップルのスティーブ・ジョブス、グーグルのエリック・シュミット、ソフトバンクの孫正義さん、みんな1955年生まれです。
みな、その時代に育った人に偶然「練習量が圧倒的に多くなる環境」があったということです。
思春期とパソコンの黎明期が重なって、プログラミングにのめりこんでいったのでしょう。
この「1万時間の法則」は、僕たち中年代の人間にも、大きな自信を与えてくれます。
これからでも、1日3時間を10年間、何かに打ち込めば、誰でもその道の天才になれる可能性はあるということです。
僕たちにも、まだまだチャンスは残っているのではないでしょうか?
まあ、もっと早くに知ってればなあという気持ちにもなりますけど。。。(笑
※ 僕はアフィリエイトはやっていませんので、そういう意味での紹介ではありません。念のため。